_
村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」を読んでいます。1Q84は昨年ベストセラーになりましたが、Book2はBook1の半分程度しか売れていないそうです。つまり、半数程度の人は、流行なので買ってはみたが、読めずに諦めたことになります。当然だと思います。あれを読める人が日本に100万人(人口の1%)もいるわけがありません。
村上春樹の文章は、とにかく“くどい”のです。私なら1/100で要約できると思います。彼に限らず、夏目漱石や福沢諭吉にはじまり大江健三郎に至るまで、純文学というのは非常に“くど”く書かれています。連用節が異様に長く、しかも複数あります。学校の先生に1文は40字程度に区切るように指導されましたが、大文豪達の業績を考えると、あれは嘘だったんですね。
文学に限らず、クラシック音楽も軽音楽に比べると“くどい”作風です。展開が異様に遅いです。「またそのパターンきましたか」とか、「いつまでやってんの?」とか思ってしまいます。特にベートーベンはキテますね。月光なんて私が書いたら15秒でフィニッシュです。(Am→Em→G7→Amで、終わり。黒鍵が面倒だから調も変えた。反省はしていない。) 私、自慢じゃありませんが、ピアノのソロコンサートで寝なかったことなんてただの一度もありません。バロック音楽だって、配列は数学的にみて整っていますが、特に聴いて感動することはありません。
お芝居の世界でも、歌舞伎ぐらいはなんとか解せますが、能とか狂言とかを心の底から楽しんでる客なんてたぶんいません。何を言ってるか分からないですから。同様に、オペラだってネイティブが聴いても何を言ってるか分からないんですよ(これはホントです。発声を重視しすぎて発音が台無しだから。)。きっとつまんないんです。
カルチャー、サブカルチャーを含まない、狭義の文化を解する真文化人は、試されているのです。努力し続ける忍耐が備わった人間かどうか、試されているのです。もともとは貴族の通過儀礼であったわけで、現代ではインテレクチュアルの証を得る修行に他なりません。つまらないもの、くどいもの、長いものを、全身に浴びて、耐えて、消化して、血肉にする。そんなストイックな我慢大会こそが、文化であると、そんなふうに思うのです。私はそれに耐えてでも、教養ある文化人と言われたいので、夏目漱石の「こころ」、石川啄木の「一握の砂」、太宰治の「人間失格」、小林多喜二の「蟹工船」ぐらいはなんとか読破しました。気晴らしに英語の医学論文が読めるぐらいの強い苦痛でしたが、確かに得るものはありました。ほんの少しだけですけど。ちなみにマルクス「資本論」とダンテ「神曲」は挫折しました(要約は読みましたが)。一向に理解できないことと、当たり前のことを、極限までくどい言い回しで、これでもかというほど繰り返してきます。あいつらは強敵でした。“文化道”というあたらしい道(どう)を作って、師範になるのが僕の夢です。
ダブルスペースじゃないブログもたまには文化として楽しんでください。
_
_
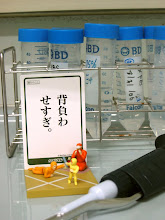
0 件のコメント:
コメントを投稿